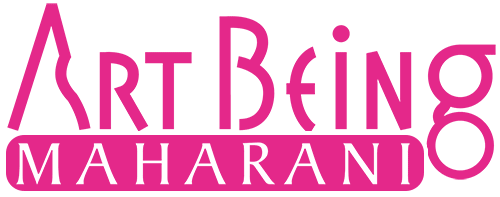八ヶ岳もすっかり春です。いえ、春を超えて夏のような日差しの日もあるくらいです。

八ヶ岳の里山に住んでる人々の多くは代々自給用の畑や田んぼをされているので、この時期は野外で畑仕事をする人の姿が増えて一気に活気付きます。

田んぼは耕運され、苗代の準備をする人たちもいます。
マハさんは田植え前にインドに行く時期なので、今のうちに苗作りの準備に取り掛かります。

友人の古民家の庭で一緒に準備をさせてもらいました。

まずは種としてとっておいた種籾を脱芒機という機械にかけます。
籾はわずかに毛羽立っていて浸水する時に水を弾いてしまうことがあるので、その毛羽立ちをとってくれる機械です。

写真中央よりやや右あたりに粉末があるのがわかりますか?脱芒され粉末化したものです。籾のまわりはツルッとしています。

脱芒している間に塩水を作ります。

その塩水に脱芒した籾をいれてかき混ぜます。

浮いてきた米は身の詰まっていない椎菜など種としては未熟なものです。この作業は塩選といい、良い種を選別するための作業となります。

浮いてきたものを掬いよけます。

残ったものが今年の種となります。

流水でよく洗って塩気を落とします。

よく水気を切ります。

今度は60℃のお湯10分間につけて消毒をします。籾にはさまざまな菌が生きているので、病気を防ぐのに有効です。

冷たい水で洗い流して温度を冷まします。
友人作の浸水マシーン。

10日ほど浸水してゆっくりん籾が目を覚ますのを待ちます。その間新鮮なお水と空気を送るために流水にするための装置です。
この日の作業はここまで。

こうして今年も天日干しササニシキ作りが始まります。