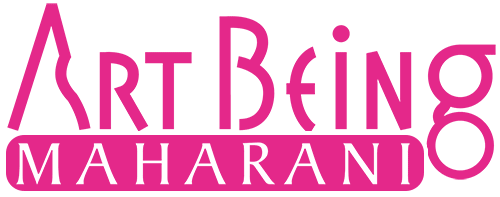初霜がおりました
八ヶ岳標高900mほどの我が家は昨日初霜が降りました。

まだ夏野菜の名残がぼちぼち取れる畑もこの朝を境に一瞬にして景色が変わります。

白い結晶に覆われた草花は儚くも美しく、白く吐き出される息もまた「この季節がやってきた」と心躍るのです。

迎えた大豆の収穫期
そんな季節に八ヶ岳の農的暮らしの一年の最後の大仕事とも言える大豆の収穫期を迎えます。

梅雨の明ける頃に種を播き、

夏に青々と茂る葉を眺め、花が咲きサヤが膨らむのを心待ちにします。

私たちが育てている大豆は秩父在来種の『借金無し』という大豆です。

大きくて丸い大豆で、甘味があります。煮豆で食べても美味しいです。借金無し大豆はその名前が示すように、借金も作らなくていいほど多収の実つきのいい大豆です。私たちはこの大豆を農薬や肥料を使わず毎年育てては種を継ぎ、早10年を超えます。

そしてアートビーング代表が育てる天日干し米を醸して麹にし

煮大豆と合わせて手前味噌も作ります。

豆乳や豆腐、納豆なども作っています。おからも食べますが鶏にも分けています。

大豆は畑の土を肥やしてくれますし、日本人の食文化には欠かせない食材として自給を続けてきました。
今年は高温多湿な気候の影響で様々な作物への影響があったとあちこちから聞こえてきます。

猛暑によりカメムシが大量に発生し、各地のフルーツ農家さんの被害は深刻で農薬使用を増やすことも致し方無しとも聞きました。大豆もカメムシの被害は受けやすいので深刻です。
私たちの大豆は多少カメムシさんに齧られても気にしませんが、高温障害により乾燥が遅い、発育にムラがあるなどの影響が少なからずあり、例年の発育状況と異なり心配も多かったように思います。しかし畝間を広く取り風の抜けをよくしたり、畝を高くして水切れをよくするなどの工夫をしてなんとか収穫まで漕ぎ着けました。
まずは大豆の刈り取りを

秋晴れの空気の澄んだ今朝、富士山も姿を表して気持ちが良いです。

大型農業ではないので刈り取りは乗用の収穫用トラクターではなく、アナログな刈払機といういわゆる草刈り機です。

一本一本茎元を切って倒して行きます。

それを逆さまにして合掌型に傘状に組んでいきます。

このまま1週間ほどおいてカラカラに乾かします。

この乾かし具合も大切で、カラカラにしたまま置いておくとサヤが爆ぜて大豆が土に落ちてしまうのです。もちろん次の世代を残すための自然な営みなのですが、栽培している以上しっかり分前はいただくため適期を見極めます。

育ててみてわかるのですが、大豆だけでなく穀物全般収穫からの工程がたくさんあります。乾燥の後は脱粒して豆とサヤを分け、ゴミを取り除き、傷物や大きさを選別したり、食べれるようになるまでにとても手がかかります。

そういう工程を見ていると自分の元に届く食べ物の価値を実感します。それはまるで日々何気なく口にしているものの生きた物語を読んでいるようです。そこには長い長いプロセスがあります。

そうしてまた、手元に残った大豆たちと共に年を越して春を待つのもまた特別愛おしく感じるものです。もう10代も自分の手で継がれてきたお豆さんと思うとなんだか可愛いと思いませんか?^_^
サヤからお豆を取り出す脱粒という作業も楽しみです。今年はどれだけ愛おしいお豆さんがやってくるでしょうか。
sameera