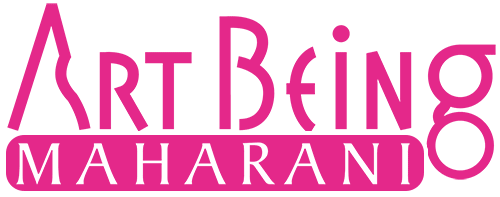水稲用苗の播種を行いました
ゴールデンウィークを迎え八ヶ岳は田んぼの代掻きシーズン。どの田んぼにも水入れが始まりました。

先日浸水した籾も目覚めたので、この日米の苗を作るために播種(はしゅ)を行いました。実はこの翌日マハさんはインド出張を控えていて、この後夜に成田に移動するという過密なスケジュール。
今回も自給農園めぐみのさんのスペースと道具をお借りして苗トレー80枚分の播種をさせてもらいました。

まずは育苗トレー(苗箱)と呼ばれるトレーに土を敷きます。

こんな道具で土の高さを均一化します。

諸刃になっていて、稚苗用と中苗用の深さが選べます。今回は黒いラインが引いてる中苗用の高さになる方で土の深さを揃えました。

その土の上に今度は種まき機を使って播種。コロコロと滑らせていくと均一に種が落ちていく仕組みですが、滑らせる速さで落ちる量もムラが出るので慎重な作業です。

多少のムラは手播きでカバーです。

次は播いた種に焼き土を覆土します。苗を管理しやすくするために雑草の種を焼き切った土です。
個人農家さんはご自分で土を焼いて作る方もたくさんいます。めぐみのさんも昨年までそうされていましたが、毎年お米が予約で完売になってしまうほど人気で苗の数も激増。なかなか手が回らなくなってきました。
ここでも専用の道具を使ってトレーナーキワまで土が入るように均等に均して掻きとります。

この後発芽までこの水やりしたもので過ごすので、一枚ずつたっぷりです。

80枚!!やり切りました。実はこの一枚一枚が結構重いのです。なかなか腰にきました。
このあとはこれを乾燥しないように覆って保温して芽出しのため置いておきます。
陸稲プロジェクト
ここまでは例年の水田用の苗作りでした。
しかし、マハさんは密かなプロジェクトを昨年から初めています。様々な陸稲実験です。

稲を水田で多年草化して成功されてる事例はたくさん聞くのですが、ここ八ヶ岳は寒冷地。なかなか越冬するのにも、水路の問題や気温の問題など条件がきつく工夫が必要になります。
また水稲をやるには水の確保はもちろん、様々な機械や燃料も必要になります。誰もが家族分くらいの米を自給するにはそれらをみんなが揃えるのは難しい。だから庭や小さな土地さえあれば育てられる陸稲を育てられるようにしたい!というのがマハさんの考えです。

昨年実った陸稲の試食のため、アナログな足踏み脱穀。

こちらは陸稲の種取り用の種籾。

こちらも手作業。

手播き。

陸稲の課題は除草の問題です。
今年は昨年大豆を植えた畝の間に冬のうちに小麦を播きました。小麦の雑草の抑制力はすごいのでそれを期待して、今年は大豆を刈り取って窒素固定した畝に種を直播して行きます。
あくまで実験と研究、トライアンドエラー。
うまくいく保証はありません。米は八ヶ岳では年に一回しか作れないので、年に一つしか試せませんが壮大な自由研究を楽しんでいます。
今年はどんな年になりますでしょうか。熱い農シーズンがまた始まります。
sameera